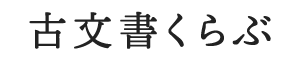ウナギの国際取引規制は日本いじめ【第二のクジラ問題】

衝撃的なニュースでした。
2025年11月24日、
ウズベキスタンで開催されたワシントン条約会議で
ヨーロッパウナギの減少に伴い、見た目も似ている
ニホンウナギも規制対象とすべきだとして、
EUとパナマが規制を提案してきたのです。
日本は世界一のウナギ消費国ですし、
そのうち7割は海外からの
中国産などの輸入に頼っていますから、
これが採決されれば輸入ウナギの価格高騰により
国産ウナギも連動することになります。
すでにウナギは高級食材となっていますが、
ますます高嶺の花になってしまうことでしょう。
「土用の丑の日にうなぎ」なんて風流な習慣も
庶民には幻となってしまうかもしれません。
このニュースを聞いたとき、
オールドメディアのフェイクでは?
と疑ってしまいましたが
よく調べると本当でした。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、
これは紛れもなく
「第二のクジラ問題」です。
クジラやウナギを食する習慣のない国にとっては
痛くも痒くもない提案でしょうから、
日本いじめに他ならないわけです。
これもグローバリストの策略でしょう。
こういったことがあるから、日本は輸入に頼らず
あらゆる食材で自給率を上げていかなくてはならないのです。
そのためには生産者さんの数が必要ですし、
そうした方を大切にしないといけません。
日本は大企業ばかり優遇されて、
中小企業や一次産業などはずっと冷遇されています。
そのしわよせが結局わたしたち国民に回ってくることを
しっかり理解しないといけませんね。
ここで気を取り直して
古文書でのウナギにまつわる記述をひとつご紹介したいと思います。
山東京伝の『骨董集』から「かばやき」に関しての考察です。
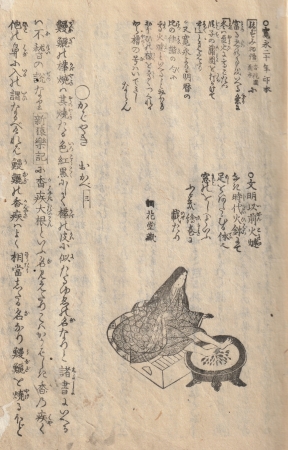
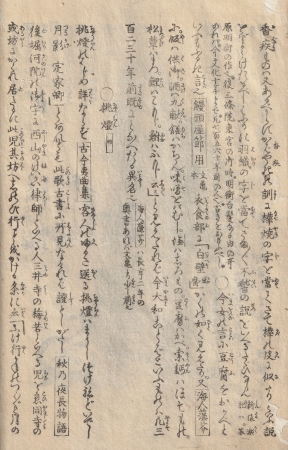
「鰻のかばやきは、その焼き色が紅黒で
樺の皮に似てるがゆえの名であると
数々の書物で言われるのはデタラメである。
『新猿楽記』に香疾大根(かばやきだいこん)
という言葉があるが、これは香ばしいかおりを
早く人の鼻に届けるという意味である。
これを鰻のかばやきとはよく言ったものだ。
鰻の焼けたものほど香ばしいものはあるまい。
香疾に樺焼の字を当てて、樺の皮に似ている
とされる説は作られたものだろう」
現代語訳するとこうなります。
読むだけでよだれが出てきますね。
この『骨董集』は文化10年(1813)の作。
この時点ですでに過去のものとなった言い伝えなどを
考察した考証随筆というジャンルの作品になります。
今でいうところの論文みたいなものです。
200年以上も前に鰻のかばやきがあったのは明確ですから、
これも紛れもなく日本の食文化なのです。